ビジネス著作権検定受検について
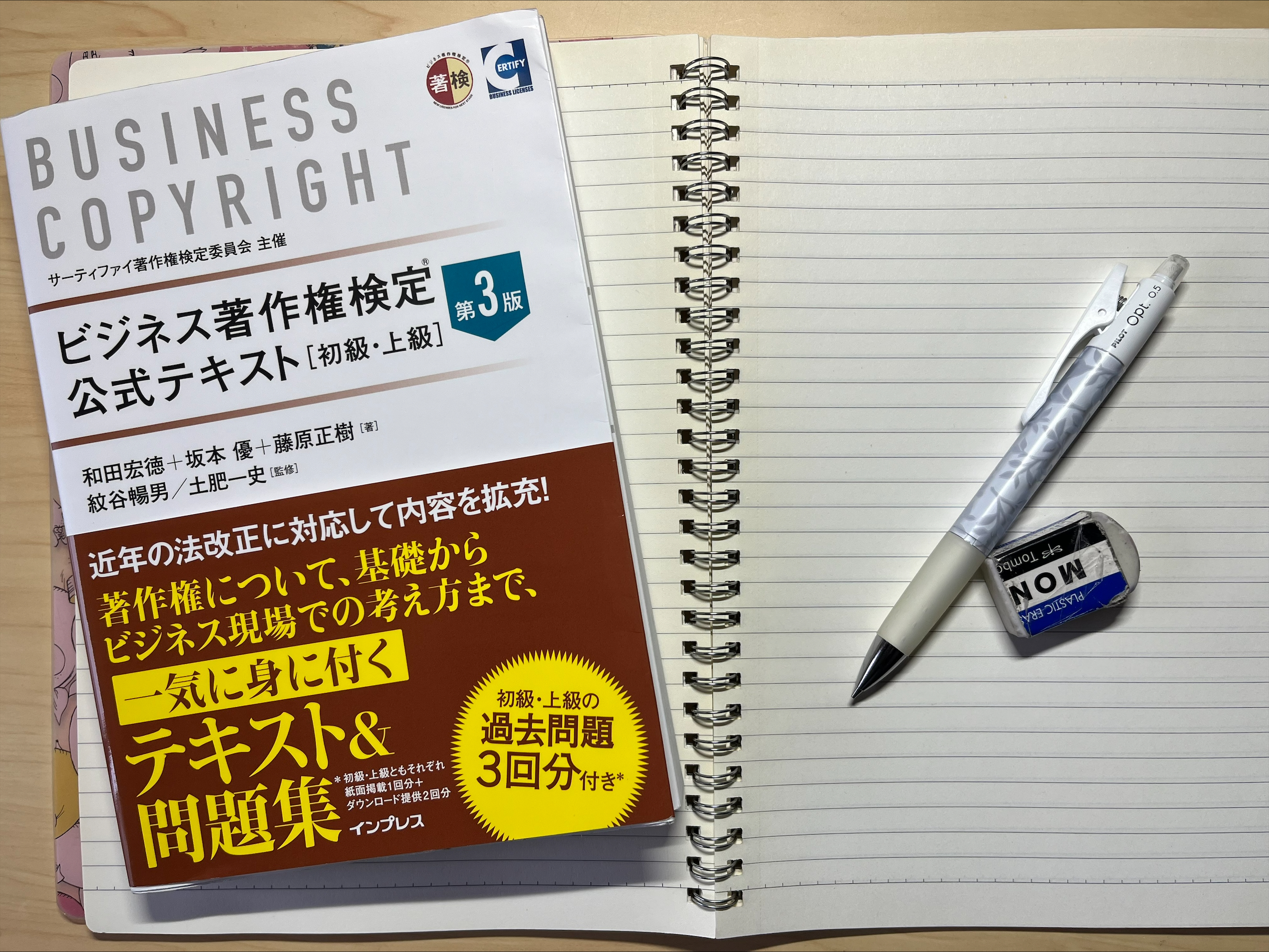
はじめに
ビジネス著作権検定とは、「著作権検定委員会」が主催する、日本で唯一の著作権を専門とした資格認定試験です。本試験は、著作権に関わる過去の判例などを基に作成されており、実践的な問題が出題される点が特徴です。難易度はBASIC・初級・上級の3段階に分かれており、私たちは今年度7月に初級を受検し合格した後、1月に上級へ挑戦しました。
本稿は、ビジネス著作権検定を受検した私たちの学びや得た考えなどについて記したものです。
山本果奈
今回私がビジネス著作権検定初級を受検した理由は、将来の就職活動に向けて、自分の知識の幅を広げたいと考えたからです。正直、最初は著作権についてほとんど知識がなく、少し難しそうだなと感じていました。しかし、授業で著作権や特許に関連する判例を研究していたこともあり、ビジネスシーンでも重要なテーマなので、挑戦することに決めました。
まず、勉強を始めたのは試験の約1ヶ月前でした。公式テキストを読み進めるうちに、著作権の基本的な概念や、著作権法がどのように企業活動に関わるのかを学びました。特に、「著作権侵害」とは何か、どのように著作物を使用すれば問題ないのかという部分が大切だと感じました。また、著作権に関する契約や、ビジネスにおける実務的な注意点についても理解を深めました。勉強法としては、テキストを一通り読んだ後、実際に問題を解きながら復習を行いました。最初はなかなか覚えられなかった用語や条文も、繰り返し問題を解くことで少しずつ定着しました。特に、過去問を何度も解くことで、試験の形式に慣れることができました。試験当日は、少し緊張しましたが、十分に準備したおかげで、冷静に解答することができました。結果として、無事に合格することができ、達成感を感じました。
この検定を通じて、著作権に関する知識が深まり、今後のビジネス活動に役立つと実感しています。また、学びの過程で自己管理能力や、時間の使い方も身につけることができ、就職活動にも自信を持って臨めそうです。
宮尾藍羽
私は、この検定に対する学習が授業の内容を理解するのに役に立つと考え、この検定を受検することを決めました。ビジネス著作権検定の学習を通じて、著作物は一括りに扱われているのではなく、その種類ごとに著作者の権利や著作権侵害の範囲が定められていることに驚きました。著作物の性質に応じて著作権法が設けられていることを学ぶことができ、授業の理解に大変役に立ちました。初級では、著作物の定義やどのような権利が発生するのかを学び、基本的な理解を求められました。一方、上級では、条件付きの問題や状況に応じた著作物の取り扱いについての知識、さらに契約や国際条約に関する専門的な内容が問われ、初級と比べて難易度が高い印象を受けました。
この検定を受検するにあたって、著作物ごとに異なる特徴に基づいて法律が定められているため、この点を理解することが重要であると考え、まず著作物の特徴を把握することを重視して学習に取り組みました。また、著作権の制限や保護期間といった関連知識も幅広く学ぶ必要があると感じました。そこで、テキストで基礎知識を一通り学んだうえで過去問を解き、不正解だった問題を振り返るという方法で学習に取り組みました。不正解だった問題は、なぜ間違えたのかを分析したうえでもう一度テキストを読み返すことが検定に合格するために効果的であり、不正解のまま放置しないことが合格に繋がると感じました。
この検定の受検を通して、著作物に関する知識を入れることができただけでなく、目標達成に向けて何をするべきか現状を分析したうえで学習を進めることの重要性を再確認できました。この経験を今後の活動に活かしたいです。
小林美緒
はじめに、これまでの私は、著作権に関する知識が一般的な情報にとどまり、詳しく学んだことはほとんどありませんでした。また、「ビジネス著作権検定」という資格が存在することも知りませんでした。そのような私がなぜ「ビジネス著作権検定」を受検することを決意したのか、また受検を通じて得た学びや感想について記します。
まず、私がビジネス著作権検定を受検しようと決意したきっかけは、ゼミの指導教員からの勧めでした。私が受講しているプロジェクト1I・2I(足立ゼミ)では、ビジネスの根幹であると考えられる知的財産についての裁判例を取り上げてチームで判例研究に取り組んでいます。この活動を通じて、著作権の種類や適用範囲など、多くの知識を学ぶ機会がありました。そこで得た知識を実践的に活かせる場を模索する中で、ビジネス著作権検定の受検を決意しました。
次に、ビジネス著作権検定を受検し、著作権の奥深さを改めて実感しました。「著作権」という言葉自体はシンプルに聞こえますが、実際には多数の権利が存在し、それぞれに細かいルールが定められています。例えば、類似する概念を持つ権利や、保護対象が微妙に異なる権利が存在し、それらを正確に理解することが重要であると感じました。また、試験勉強においては、実際の試験問題を解くことを重視し、問題文のどの部分に正誤のポイントがあるのかを意識して学習を進めました。その過程で、単なる暗記ではなく、著作権の概念や適用範囲を論理的に理解することが求められると感じました。
最後に、今回の受検を通じて、自分が知らなかった分野について学ぶことが、将来の可能性を広げる貴重な機会となることを実感しました。今後も幅広い分野の知識を習得し、自身の視野や価値観をさらに深めていきたいと考えています。また、学習の機会を積極的に活かし、恐れずに何事にも挑戦しようと改めて思いました。







